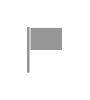ニュース・ブログ
地盤改良工事の特徴
家を造る際、地盤が強いのか?弱いのか?
その調査を地盤調査と言いますが、もしも弱い場合には何らかの地盤補強(地盤改良)工事が必要になります。
今回は、色々な補強工事の特徴をお伝えします。
1.表層改良工事

やわらかい地盤の深さが浅く1m以内の場合に用いられる工法です。
やわらかい部分の土とセメント系固化材を混ぜ合わせて重機で締固め、ローラーでならし強度を高めます。
【メリット】
・値段が安く済む
【デメリット】
・施工者の能力によって仕上がりが左右される
・土の状態によっては、発がん性物質の六価クロムの発生もある
2.柱状改良工法

やわらかい地盤の深さが2~8m程度の場合に用いられる工法です。
ドリル状のヘッドを装着した施工機で地盤改良面に直径60cmの穴を掘りつつ、セメントをミルク状にしたものを注入して土と撹拌していきます。固い地盤に到達するまで掘り進め、円柱状に固化された土を地中に形成します。
【メリット】
・施工時の音、振動が少ない
【デメリット】
・コンクリートミルクでの硬化で鉄筋は入っていないため、横からのズレには弱い
・土の状態によっては、発がん性物質の六価クロムの発生もある
・残土処分費が発生する
3.小口径鋼管杭工法

やわらかい地盤の深さが深い場合に行う工法です。地中に鋼製の杭を垂直に打ち込むことで建物を支えます。
【メリット】
・短時間で工事が完了する
・六価クロムの心配がない
【デメリット】
・支持層の無い土地では施工できない
4.砕石パイル工法

やわらかい地盤の深さが5m程度の場合に用いられる工法です。
土を掘って支持層に到達するまで穴を開け、そこに直径2cm~4cmの砕石を投入して石の柱を作ります。
【メリット】
・有害物質を発生させない
・砕石は水を通過させる能力が高いため、液状化現象対策として期待できる
【デメリット】
・地震が繰り返された際に発生した液状化現象に対応出来るか?は不安
・セメントやセメント系固化材を用いた地盤改良より施工費用が高くなる
・残土を処理する費用が発生する
・土の種類によっては堀った穴が崩れ砕石を投入する作業は困難
・地下水が高い場合作業は困難
以上の工法が良く使用されています。
それぞれの特徴があり、固い支持層までの深さや状況が様々ですが、色々な工法があることを知っておくと良いのではないでしょうか?